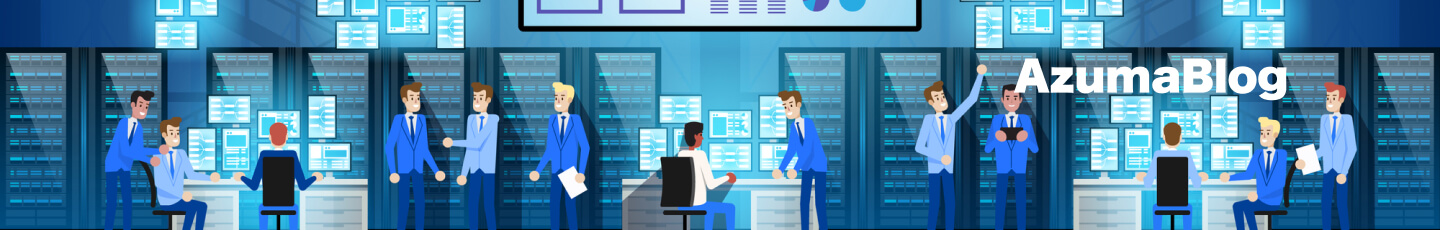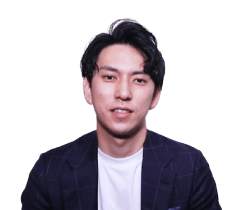中小企業診断士1次試験の【科目ごとの難易度と独学の勉強計画】
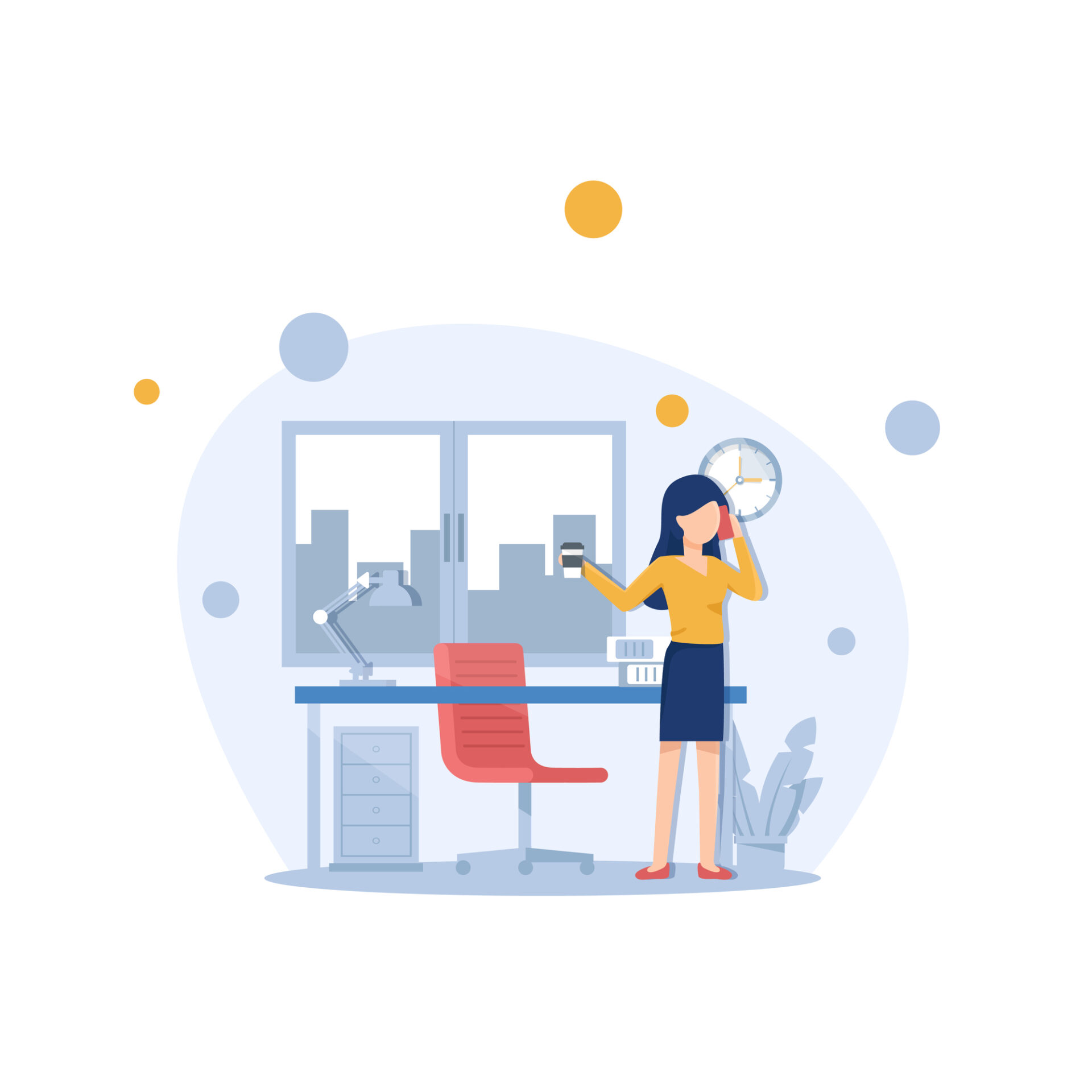
独立中小企業診断士の平井あずまです。
本日は、中小企業診断士を独学で合格するために必要な勉強についてお話ししていきます。
中小企業診断士の試験を受けようと思った時にチラつくのが「独学なのか」「受験予備校への通学なのか」ということです。
独学で合格するための勉強についてお話ししていきます。
YouTubeの動画でも同様の内容を配信していますので、合わせてご確認ください!
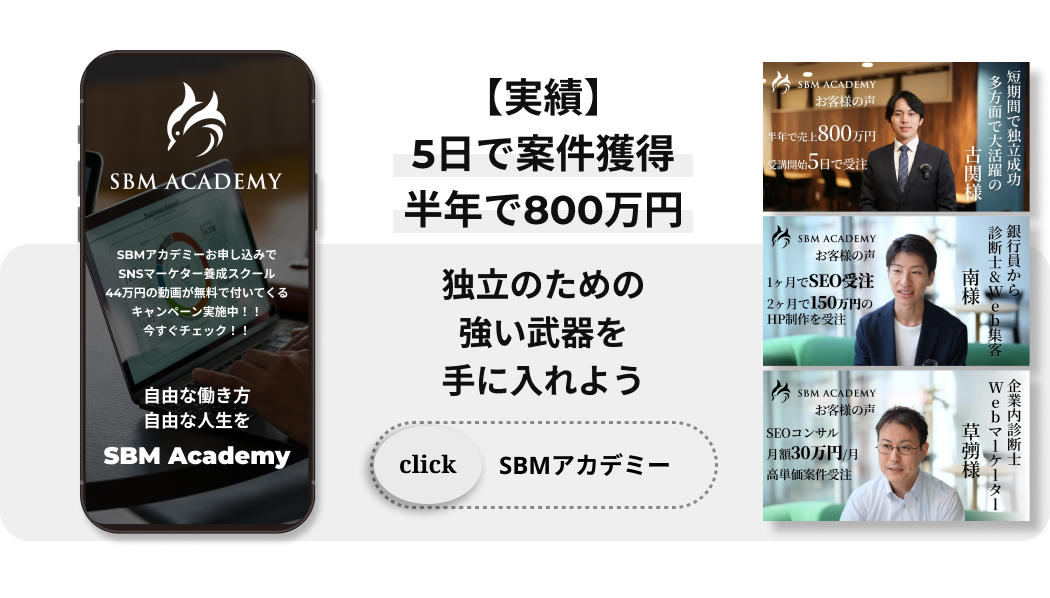
目次
試験科目の内容とは
1次試験は、全部で7科目となっています。
企業経営理論・経済学、経済政策・財務会計・経営法務・経営情報システム・運営管理・中小企業経営・政策となります。
独学合格に必須のテキストとは
まずは独学で合格するために、活用したほうがいいテキストについてお話ししていきます。
全教科共通で、TACのスピードテキストをおすすめしています。
全科目購入するとそれなりの金額となりますが、合格するとすぐに回収できると思いますので投資だと思って思い切って全て購入してみてください。
独学合格に必須の問題集とは

続いて、独学で合格するために活用した方がいい問題集についてお話ししていきます。
これも全科目共通で、TACのスピード問題集をおすすめします。
これも全科目思い切って活用してください。思い切って全科目の問題集を手に入れることが合格までの第一関門です。
独学合格に必須の過去問題集とは
続いて、過去問問題集についてお話ししていきます。
過去問題集もTACの過去問題集がおすすめです。それに加えて「過去問完全マスター」という10年分の過去問の重要な部分を集めた過去問もとてもおすすめです。
苦手な科目に関しては過去問完全マスターを追加してもいいかもしれません。
私は全科目分の過去問完全マスターを購入して勉強していました。
独学で合格するために必要な勉強時間

続いて、勉強時間についてお話しします。
一般的に必要な勉強時間
時間の計測方法で変わってくるのでなんとも言えないのですが、大体800時間程は確保したほうがいいと思っています。
2次試験で400時間程時間が取れると合格できるギリギリのラインだと思います。
私の診断士試験の経験談
私自身は必要を超える勉強をした結果、模擬試験で上位1%を一次試験・二次試験で取りましたが正直そこまで必要なかったと思います。
問題集を何周するか・過去問を何周するか問題ですがそれぞれ最低でも5周くらいはしたほうがいいと思います。私は数十周しました。
何周も勉強するときの注意事項
気をつけて欲しいのは一つの問題に固執し過ぎて次に進めなくなってしまう、ということです。
完璧主義社の方は注意しましょう。範囲が広い試験ですが40-50点分はそこまで難しい問題はありません。頻出の問題を必ずとれるようにすれば合格に近づけます。
難しすぎる問題は思い切って捨てる!というのも6割で合格の試験では必要になります。
受験予備校のメリット

受験予備校に通うメリットは、頻出の範囲をわかりやすく勉強できることです。
自分で勉強をする範囲の強弱ができない人は予備校がお勧めです。
通学と通信講座について
通学や通信講座の場合は、どの時期にどんな内容を進めていればいいのかというスケジュールを教えてくれるので勉強の計画が立てやすくなります。
独学の場合は、どのようなスケジュールで勉強をしていけばいいのかというスケジュールを立てることが難しくなります。
もし、自分で考えるのが難しそうであれば受験予備校が出しているカリキュラムのスケジュールを見てみるのもいいかもしれません。
科目ごとに取り組む順番がある
大体の進め方や科目ごとの取り組む順番など、参考にできる情報はたくさんあります。
科目ごとの取り組む順番も大切になりますので、私がお勧めしている勉強の順番についても共有させていただきます。
試験の直前きは、暗記三兄弟の「経営情報システム」「中小企業経営・政策」「経営法務」の力を入れて勉強することをお勧めします。
運営管理も暗記色が強いので、運営管理も加えて暗記4兄弟として勉強するのもいいかもしれません。
試験勉強を始めた当初は最も勉強が楽しい企業経営理論で勉強をする習慣をつけて、同時並行的に財務会計と経済学の勉強をするのがおすすめです。
どの科目でどのくらいの点数をとるのか
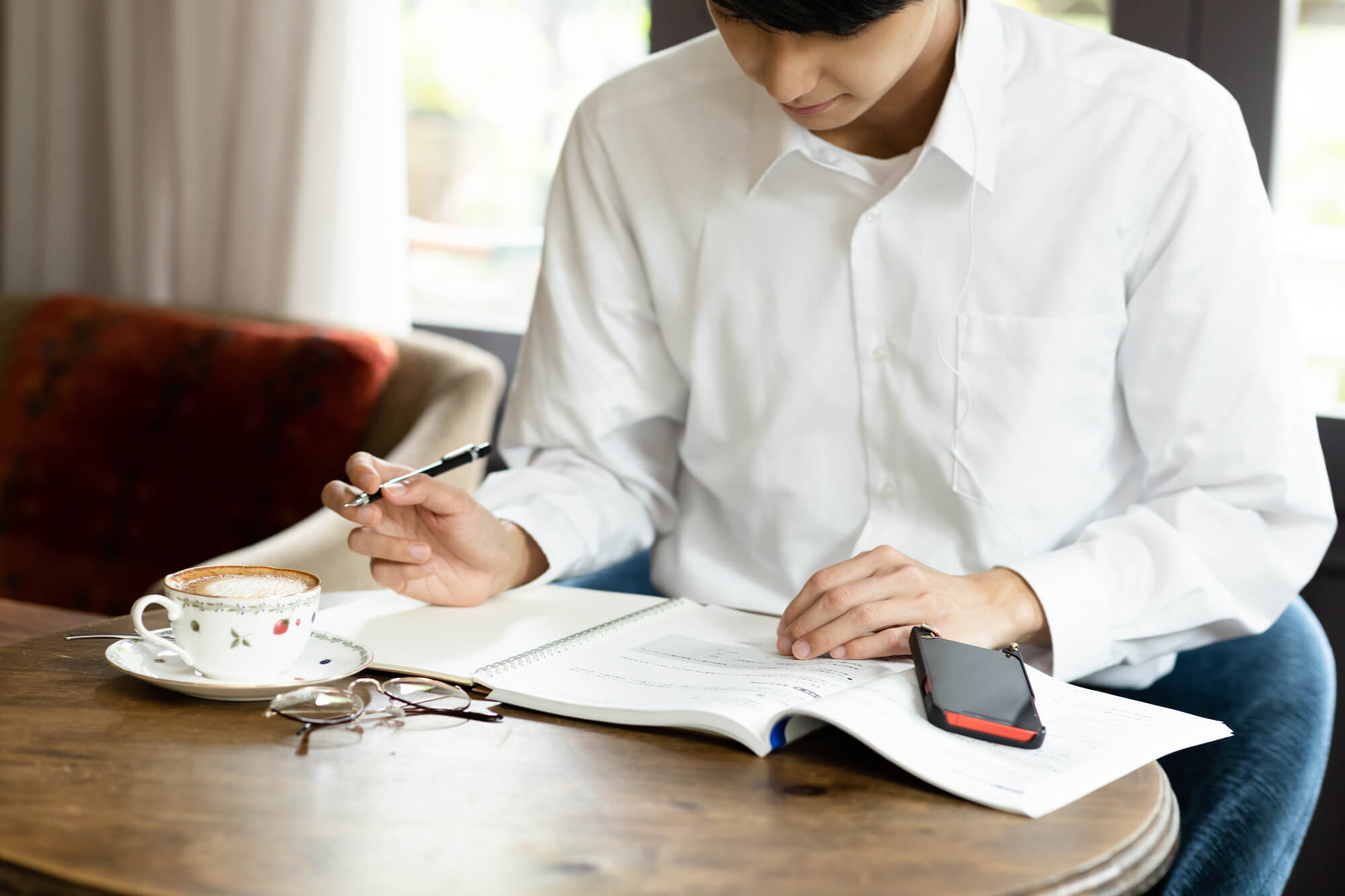
そしてどの科目でどのくらい点数をとるべきか、というお話もしたいと思います。
中小企業経営・政策を勉強しよう
最も点数が安定的に取りやすいのは「中小企業経営・政策」です。
この科目は、頑張れば頑張るほと点数が取れます。
これで点数が取れないと合格は厳しくなります。
独学・通学関係なく暗記する科目で出題範囲もある程度決まっているので、最も点数を稼ぎたい科目になります。
中小企業経営・政策で60点とれない場合、それは怠慢だと思います。そのくらいしっかりと勉強して、点数をとるべき科目です。
財務会計を勉強しよう
そして、点数も取れるし、2次試験対策とも相乗効果の高い財務会計は、しっかりと勉強することをおすすめします。
財務会計を理解しないとなかなか合格は難しいかと思います。
一次試験はなんとなく合格しちゃったということもあり得ますが、2次試験の事例Ⅳは、理解しないと合格点が取れません。
そもそもコンサルタントで決算書を読めず経営分析もできませんよね?将来の活動も想像しながら財務会計に取り組みましょう。
中小企業診断士の試験は難易度が毎年変わる
中小企業診断士試験で点数がばらつく科目もご紹介します。
毎年のことですが、科目ごとに難易度にバラツキがあります。
私自身トラウマになるくらい難化した科目が出てしまった年に受験し、とても悔しい思いをしました。
ばらつきが大きいと思う科目
愚弟的には「経営法務」「経営情報システム」はバラツキが大きいと個人的に思っています。
「経営法務」は本当にトラウマです。問題数が少ない科目は1問の点数が大きくなりますので1つのミスが命取りになります。私みたいにならないように気つけてくださいね。
独学で合格するためのおすすめの勉強方法

中小企業診断士試験【上位1%】になる独学勉強法&必須の参考書については別のブログで解説していますので、興味がある方は見てみてください。
中小企業診断士の1次試験は独学で合格が可能
結論、中小企業診断士の1次試験は独学で合格することができます。
これまで話してきたことを頭の片隅に入れていただき、頑張っていただければと思います。
中小企業診断士の資格は合格するととても可能性が広がる資格です。
中小企業診断士は年収1000万円が簡単に稼げる資格ですし、自由に働きやすい資格だと思っています。
勉強期間中はつらいこともあるかと思いますが、合格すればとてもいい未来が待っていると思います。
ぜひ諦めず頑張ってください。
もし今年ダメでも来年。まただめでもその次。あきらめず受け続けてください。

いつか一緒にお仕事ができる日を楽しみにしています!
PS:YouTubeのチャンネル登録してくれると泣いて喜びます!笑